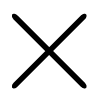BENchmarkブログ
【第645回】大好きなパイセン
先日東京のクライアント様とのミーティングをしての帰路、ついつい昔のことを思い出しました。私はサラリーマン時代、普段は名古屋で働いていたのですが、月の始めと中間に東京オフィスと大阪本社での会議に参加していました。その際に、普段会わない先輩とお会いするのですが、それが楽しくて楽しくてそれを目当てに会議に参加しているくらいでした。私をいつも弟のように可愛がってくださった先輩は東京で在籍していたのですが、いつも会議終わりに呑みに行き、散々私の悩みを聞いてくださり最後には「一緒に会社を盛り上げていこうぜ」と良い方向に導いてくださいました。後輩であるにも関わらず成果を出している私のことを敬意を持って携わってくださり、時に私が天狗になり傲慢なところが出てくると先輩としてしっかり叱ってくださり、独立した後も毎年の年賀状で「いつもブログ見てるよ」と温かい言葉を添えてくださり、私の中では恩人であり、カッコいい先輩であり、お兄ちゃんのような存在です。会議が終わって呑みに行き、新幹線も隣の席でいつの間にかキヨスクでビールを買ってくださっていて、「まぁ射場、呑めよ」とビールを差し出してくださり。私は先輩に与えてもらいっぱなしで卒業しました。「こんなカッコいい先輩になりたいな」「こんな粋な大人になりたいな」と、私の道しるべになってくださった方です。またお会いしたいな、また一緒にお仕事をさせていただけたらどんなに幸せだろう、そう思っても現実はなかなか難しいものです。だってお互い忙しいもの。今上司や先輩がいらっしゃる方、その環境はとても「有り難い環境」です。「有り難い」とは「有り得ない」ということです。時には口うるさく聞こえるかもしれません、煩わしく感じるかもしれません。ただ、10年後、20年後必ず「あの人にもっと感謝を伝えたい」と思うときがくるはずです。その際に感謝を伝えられる環境であればそれに越したことはないのですが、中々そうはいかないもの。今の当たり前がいつか当たり前でなくなる前に恩を授けていただいた方には感謝を十二分に伝えていても損することはないんじゃない?
【第644回】部下の遅刻を直す方法
先日とあるクライアント様でスタッフの一人が遅刻癖がなかなか抜けずに困っていらっしゃいました。そのスタッフの方はとても愛嬌のある方で、素直で真面目で優しく私自身大好きな子なのですが、とにかく朝が弱いとのこと。会社でもペナルティを設けてなんとか改善を図ろうとしていたのですが、なかなか治らず本人も若干諦めムードでした。社長からその相談を受け、その担当を呼び出して私が「これから君が遅刻する度に私が罰金¥1,000をこの会社に支払います。」とお伝えしたところ、なんとそれから約3ヶ月遅刻0です。これはたまたまその子が「人のために一生懸命する人」「人に迷惑を掛けたくない人」だったからこそ上手くいったことですし、私もその子を信じて言ったことだったのですがここまで上手くいくとは自分でも驚いています。よりその子が愛おしくなり、これからも一緒にお仕事をさせていただきたいなと思っています。そして何よりその提案を何も言わずに信じて受け入れてくださったその社長に感謝です。人を育てるというとたいそれたことですが、その人に合った対応ができるのはその人を知っているからこそです。人の育て方は何が正しくて何が間違いかはあやふやです。A君で成功したことがB君ではうまくいかないなんてことは日常茶飯事です。ただ、それでも部下と一緒に成長することを望むことが上司や年長者としての役割じゃない?
【第643回】来年もあるって保証はないんだぜ?
皆さん仕事においても人生においても「計画」は立てていらっしゃるでしょうか?短期計画、中期計画、長期計画。私自身も株式会社BENchmarkの短期、中期、長期計画は15年先まで立てているのですが、一つ注意していることは「不測の事態でいつ終わっても大丈夫な計画」にしています。仮に私が病気や事故で亡くなったら、家族の介護などで働けなくなったら、そんなときでも取引先に迷惑をかけず、残された家族が金銭的に苦労をしないように準備万端です。よく計画を立てる際に「それは来年から着手しようかな…」と、計画というよりはただの「後回し」にしたいだけの人とお話しする際にお伝えさせていただくことは「来年があったらいいですけどね」ということ。来年も五体満足でいれたらいいですけどね、来年も会社が存続していたらいいですけどね、来年も生きていられればいいですけどね。「後でやろうは馬鹿野郎」という言葉があるくらいで、馬鹿野郎とまでは言いませんが「明日もある」「来年もある」「10年後もある」と当たり前に思っていると、人生を無駄遣いしちゃいがちになりそうです。大切なことは明日あるのか、10年後があるのかはわからないけれど、「今」をしっかり丁寧に生きるということ。その積み重ねが未来の自分を作るのです。一日腕立て10回でも毎日やったら3650回。一日¥100課金したら¥36,500。それを10年続けたら¥365,000。未来があるかどうかは分からないけれど、少なくとも「今」を大切にすることが豊かな人生を作る第一歩なんじゃない?
【第642回】本当の努力をしているとき
多くの成功者に共通する「努力」。努力した人が必ずしも成功するわけではないが、成功した者は皆努力している。byベートーヴェン。ただ、本当の努力をしているときは、ある種の覚醒モードに入っているのでやっている本人は「努力している」という実感が無いのです。「努力」と聞くと、目標必達のために汗をかき、我慢や忍耐の上に成り立つ成功をイメージしがちですが、例えばパチプロの人が朝から並んで良い台を陣取り、ノートにその台の傾向と対策を書き取り何度もトライする。競馬で馬をじっくり観察し、過去のデータとも照らし合わせ賭けの精度を上げる。普段ギャンブルを一切しない人からすれば、これは「努力」となるかもしれませんが、やっている本人は努力だなんて思っていないでしょう。私自身起業してから努力という努力はしていないと思っています。なぜなら「楽しい」からです。先日久しぶりに経営の健康診断がてら定期的にやっている顧問会計事務所との打合せの際に「毎月よくこれだけのクライアントを対応できますね」と言われたのですが、私自身毎日自分で「この人とお付き合いしたい」と思った人と「より良くなるためのミーティング」をする、そのために日々色々な情報を収集する。実際に試してみて分析して改善に繋げ成果を出していく、この一連の流れが楽しくてしょうがないのです。ゲームやギャンブルよりもよっぽど楽しいのです。私は普段から夜呑みに行きません。理由としては家族の時間を大切にしたい、自分の時間を大切にしたいということもあるのですが、「呑み」より「ミーティングをしている時間」の方が100倍楽しいからです。これも人から見ると「あの人は仕事ばかりで努力している」と見られるかもしれませんが、全く努力していません。だって楽しいことしかやっていないからです。クライアント様の成長と成功が自身の成長と成功に繋がる。どんどん求められること、求めてくださる人の数が増えてくる。0から始まった事業がどんどん私の思った以上になってきている。経済的にも精神的にもどんどん豊かになってきている。「大人が本気で遊ぶとそれはビジネスになる」という言葉がありますが、まさにその通りで「本気で遊んでいる」という感覚です。もしあなたが「俺ってば努力してるな~」と思って今を耐え忍んでいるのであれば、その次のステージがあるのでワクワクしながら目指してみてもいいんじゃない?
【第641回】マーケティングをジャックされていないか
経営にはたくさんのスキルが必要です。営業力、経営力、そしてどんなに良い商品を持っていても見つけてもらえないことには人の手渡らないので「発信力」いわゆる「マーケティング力」が何よりも重要だと思うのですが、多くの上手くいっていない経営者が「マーケティング」を「他者に丸投げしている」ということがあります。ホームページ業者に丸投げ、広告代理店に丸投げ、ひどいところでは責任がない素人のパートスタッフに丸投げ。また、ホームページ業者や広告代理店は悪質な会社が多いので敢えて相手が分からない専門用語をつかって「分かりづらくさせることによって何も言わせない状況」に持っていく業者が非常に多いので、知識が無く、その上プライドが高くて「それどういうこと?」と聞けない経営者だとまんまと丸め込まれてしまいます。自分で分析して自分で対策を考え進めていくのは他者の力を使っているのであればいいのですが、「〇〇さんがこう言ったから」「〇〇さんがこっちが良いっていうから」という理由でマーケティングを丸投げしているのは、せっかく自由な飛行機の旅を楽しむにも関わらず行先等自分で決められないハイジャックされている状況と一緒なのです。残酷なのはジャックされている状況を分かっていないということ。幸い今インターネットやSNSで素人でも簡単に情報が手に入る時代です。webの専門用語を少し頭に入れておくだけで相手に騙されずに済みます。ググればいいのです。私も多くのクライアント様がホームページ業者との打合せで「相手が何を言っているかちんぷんかんぷんだから同席してくれ」という理由でホームページ業者と打合せさせていただく機会が多々ありますが、現状約60社ほどのホームページ業者、広告代理店とミーティングしてきてまともな会社は1社のみ。あとは根拠のない適当なことばかりを言って高額請求する詐欺軍団ばかりです。騙す方が圧倒的に悪いのですが、騙されないようこちらも知識武装していかないといけません。あなたは、あなたの会社がどのような人に、どんな方法で、どんな金額で、自社の商品やサービスでどのように喜んでもらうかを考えた上で自社の情報発信が「的確」に出来ていますか?