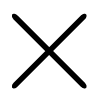BENchmarkブログ
【第728回】働きたくないけどお金は欲しいという社員にお金を払えますか?
例えばあなたの会社のスタッフで「会社に来たくないんですよ、日中はゴルフとかしたり遊んでたりして忙しいんですよ、呑みに行くときは仕事として行くんで会社の経費を使わしてもらいたいんですよ、お給料は誰よりも欲しいんですよ」というスタッフがいたらどう思いますか?私であればフルボッコですね。おそらく多くの経営者も同じことを言うのではないでしょうか?「ふざけるな!」と、「てめぇ、大概にしろ!」というだけではなく、行動力のある人であれば即刻解雇にするかもしれません。やる気がないだけではなく、会社の士気を下げる存在だからです。でも、たまにこれを平然とやってしまうスタッフがいます。それは「社長自身」です。社長もスタッフの一員です。だからこそ、社長だけ特別ルールでやっている会社は成長しないどころか、優秀なスタッフが愛想を尽かしてどんどん離職していきます。特に基本日本人は「成果には努力が必要」というマインドを根強く持っているので「頑張らない人=成功してはいけない」「怠けている人=成功するべきではない」という思想があるので、そこらへんを意識して仕事に取り組まないと会社の寿命は非常に短命で終わります。ではスタッフがいない会社の社長はどうか?これも同じです。スタッフがいなくても取引先、協力業者はしっかり立ち振る舞いを見ています。基本長く成長し、成果を出し続けている会社の経営者は「真面目」です。誰よりも働きますし、誰よりも真面目ですし、誰よりも謙虚ですし、誰よりも自分に厳しい方ばかりです。だからこそ「アホ」とは付き合わないのです。社長が歯を食いしばり汗水流してそれでも希望と無限の可能性に心を躍らせ働いていると、きっとついてきてくれる人はいます。それでも付いてきてくれる人がいない場合は、スタッフの入れ替えも考えてもいいかもしれません。ただ、その前に経営者は客観的に「自分の立ち振る舞いが会社の長として正しく振舞えているか?」を見直してみてもいいんじゃない?
【第720回】新しい情報=良い情報ではない
商売を続けていて、なかなか成果が思うように出ない場合にどうしても「新しい情報」を求めてしまいがちです。YouTubeの活用方法、SNSの最新の取り組み方など、最近ではAIを活用したマーケティングなど日々新しい情報が飛び交っているのですが、ここで気を付けないといけないのは「新しい情報=良い情報」という訳ではないのです。先日本屋さんで初刊1987年の本を購入しました。今から30年以上前の本です。内容は著名な経営者の商売のハウツー本なのですが、今でも十分通用する、むしろ今だからこそ必要なことが網羅されていました。どれだけ科学が進化し、便利なものが溢れてもそれを扱うのは人です。人の進化はそこまで早くありません。だからこそいまだに聖書や般若心経の需要があるのです。商売も同じ、基本、原理原則は昔からそこまで変わりません。もし今行き詰まっているのであれば、新しい情報をインプットする前に昔学んだことを見返してみるのもいいんじゃない?
【第709回】弱音の怖さ
言葉遊びですが、「弱音」は「弱い根」を張り、弱い根は弱い木を作りその木は「弱気」になる。という言葉を聞いたことがあります。生きていると弱音を吐きたくなるときもありますよね。誰かに聞いてもらって「大丈夫だよ」と言ってもらい安心したいときもありますよね。ただ、弱気な言葉は確実に着実に弱い根を張り詰めていくのです。特に企業のトップが弱い根を張ってしまうと、それはたちまち社員だけではなく取引業者にどんどん伝染していきます。「そんな大げさな」と思われるかもしれませんが、それだけ弱音を吐くということは商売をするにあたってリスクを伴うということなのです。弱音を吐きたいときこそ強がってみる。それこそが大人の振る舞いってやつじゃない?
【第705回】大きな成功より大きな失敗をしない
人生でもビジネスでも「はじめてやって大成功」という確率は非常に低く、何度も挑戦して改善して、挑戦して改善しての繰り返しによって成功に結び付いていきます。にも関わらず、会社を潰す多くの経営者が「大きな成功」を目指して「大きな失敗」をした結果会社を倒産させてしまうという結果になってしまいます。「失敗前提」と考えると、成功するかどうか分からないものに一発で多額の資金を投入して勝負に出てしまうと「次の挑戦につかう資金」を無くしてしまうので再起不能となってしまいます。大きな成功をするよりも「大きな失敗をしない」と意識し、小さな失敗を重ねることによって「大きな成功」に繋がることを知ると、時間の使い方、お金の使い方も少し変わってくるんじゃない?
【第702回】財布にお金が入っていないのに買い物をしない
2020年1月に起業して早くも4年経過しました。輸入商社時代にお世話になった社長がお亡くなりになったことが起業のきっかけの一つでしたが、社長からはたくさんのことを教えていただきました。正確には社長は物静かな方でしたので、社長の考えや思想を上司や先輩から教えていただいていたのですが、その中の一つで「財布にお金が入っていないのに買い物をしない」という言葉がありました。当たり前のことなのです。子供でも分かる当たり前のことなのですが、世の経営者の多くがこれが出来ない。わざわざ銀行から運転資金を借りて自分の身の丈に合っていない事業に手を出して身を滅ぼす。大の大人なのに当たり前のことが出来ないのです。ただ、当たり前のことだからできないのかもしれません。気持ちの良い挨拶をする、間違ったときは謝罪する、ゴミは拾う、整理整頓をする、こういった当たり前のことが大人になると出来ない、もしくは大人になっても出来ないからなかなか成果に恵まれないのかもしれません。弊社は起業してからお陰様で借入¥0です。銀行から「射場さんだったら¥1億以上融資できますよ?」と言われても「借りてどうするの?必要ないです」「ですよね」というやり取りです。弊社クライアント様で年商2億~5億規模の企業でも銀行借入が¥0のクライアント様は全体の4割くらいでしょうか?借入しなくても全然余裕なのです。経営者の中には「銀行からガンガン借りられるだけ借りて、事業を大きくして早く軌道に乗せるためにも借入しないといけないんだ」という方もいらっしゃいますが、商売は人様あってのこと。お客様はもちろ、取引先、スタッフのことを考えると博打はしてはいけないのです。博打は自分のお金で、人に迷惑が掛からない規模でやらないといけないのです。商売の鉄則は短期的に成長させるのではなく、じっくりコツコツ積み上げて継続していくということです。今まさに銀行から借り入れでもして事業をしようかな?と思っていらっしゃる方がいるのであれば、改めて自分の財布の中身を見て考えた方がいいんじゃない?