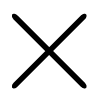BENchmarkブログ
【第595回】パクられたら勝ち
先日とあるクライアント様が「〇〇って会社、うちのやり方をめっちゃパクってくるんだよね!」とプンスカしていらっしゃる姿を見て私がお伝えさせていただいたのは「やったね!」です。相手がキョトンとされていたのですが、なぜ私がそうお伝えさせていただいたかと言うと、パクる人はその相手に「魅力があるからパクる」のです。成果が出ていそう、オシャレ、カッコいい、センスが良い、色んな理由はあるのですがパクる理由はポジティブです。「あんな会社になりたくない」と思うところのノウハウをパクる人なんていませんよね?パクられることは光栄なことなのです。私も相当色んな会社にチェックしてもらえているので相当パクられます。ただその時は純粋に嬉しいです。むしろ「これに気付くとはなかなかやるな」と「これをパクるとは、この人分かってるな」と、若干悦に浸っていてパクってくださる人に親近感すら感じます。パクられて怒るのは「新しいものをつくる自信がないから」。ただそれだけなんです。新しいものをどんどん作っていたら、むしろ「それパクるの!?それもう遅いよ!パクるならこっちよ!」とさえ思えてきます。自分のノウハウやアイデアを全然知らない人が「これだ!!」と言ってパクってくる。これってなかなか光栄なことじゃない?
【第594回】行動目標、行動実績
売上目標、粗利目標を掲げる会社はあるものの、その成果を出すための「行動目標」を掲げる会社は意外に少ないものです。行動目標とは、例えば営業の場合ですとその成果を出すために何件の訪問をしなければならないのか?そして内新規は何件?既存は何件?その中でも大手は何件?中小企業は何件?ちなみに私がサラリーマン時代は行動目標を毎月60件ほどに設定していました。週の一日は事務処理に設定していたので、週4日、商談だけではなく、納品した現場も回るので一日3~4件ほど訪問、これは多くもなく、少なくもない数字です。これを基準に考えると月の訪問件数が40件だと「あれ、今月全然回れてないなぁ。なぜ?」であったり、例えば部下や後輩が「今月あいつ80件も回ってるなぁ、おそらく商談になる前に断られてるんだろうから今の内に修正かけとくか。」という感じになってくるのです。目標を立て、実績を確認する。売上が出来るのは当然動いているからこそ。売上目標を立てる際は、行動目標もしっかり立てて進めていったほうが色々見えてくるもんもあるんじゃない?
【第593回】営業利益率31%
営業利益率とは、経営における利益効率を示す数値です。経営の効率性や安定性を判断したり、経営状況の見直しに活用したりできるため経営者にとって利益率を把握することは欠かせない指標です。そもそも営業利益とは簡単に言うと売上から仕入れや販売にかかった費用、人件費などを差し引いて手元に残った利益の金額のことです。これが0%だと当然危険、5%だと標準、5~10%であれば優秀、10%を超えるのは超絶優良企業なのですが、高ければ高いほど良いかというとそれは業種にもよるのですが、社員がいる会社で15%を超えると「社員に還元せず貯め込みすぎ」という見方も出来るので表面的には分かりづらいのですが、仮に弊社はどうかと言いますと、株式会社BENchmarkのカテゴリーは「コンサル業」になります。日本で一番コンサル業として営業利益率が高い企業がM&Aキャピタルパートナーズで28.5%、住宅業界でも有名な船井総研で14.9%。法人成りしてたった1年の株式会社BENchmarkの営業利益率は31%です。これもひとえにクライアント様、協力してくださる業者様のお陰です。利益を残すコツは至極シンプル。「お預りしたお金を無駄遣いしない」これだけなのです。当然利益が多いと納付する税金の額は多くなりますが、それはそれでOKなのです。もしあなたの周りに偉そうにして色々アドバイスをしてくるコンサルや経営者がいたら「ちなみにおたくの営業利益率はなんぼのもんですか?」と聞いてみてもいいんじゃない?
【第592回】「偉そうな人」は偉くない
人間不思議なもので、本能的になのかは分かりませんが「真逆に見せる」という傾向が見受けられます。お金がない、余裕がない人ほど派手に見せる、お金がある人は地味に見せる、悪い人は良い人を演じ、本当に良い人は「厳しい人」「とっつきにくい人」と見られる。全ての人がそうではないのですが、自身の本質を見抜かれたくないのか性分とは逆の見せ方をする人がいらっしゃいます。私自身多くの経営者と携わる中で想うのが「偉そうは人」は偉くないということ。偉そうな人は自分に自信が無いから大きく見せる、現に様々な企業の懐事情を知る銀行員や税理士と話していると、高級車に乗っている人ほど金銭的な余裕はないとのことです。偉そうな人は無知だからこそ人に恐怖や圧力で押さえつけ気持ちよく動いてもらうことのやり方が分からない。そうなるとどうなるか?当然そんな人の周りにいるのは「力が無い人」ばかりになってしまうので、本人はお山の大将を気取っていて表面的には気持ちよくなっているのですが、ポンコツばかりが集まる組織は当然成果がでるどころか様々な問題が発生するため通常より、より一層気苦労が絶えないのです。本当に偉い人は自身よりも能力の高い人が周りに集まってきます。だからこそ、本人があくせくしなくても周りに助けられて時間も経済的にも何より心にも余裕が生まれるのです。「偉そうな人」は偉くない。これだけ覚えておけば、新規で営業する際に仮に相手が「偉そうな態度」を取る人であれば、「あ~、ダメな子だ」と思って適当に相手をするか、私のように「あ~(あなたと携わる)時間がないからまたどっかで機会があれば~」と言って最初から携わらないのも心身共に健康でいられる秘訣じゃない?
【第591回】市場の状況
今年の3月、4月は建設業の倒産が増えました。人手不足や材料・人件費の高騰、コロナ融資の返済など理由は多岐に渡ります。そして5月6月は飲食店の倒産が増加しています。こちらも理由は建設業とそんなに変わりません。生活保護の申請も、コロナが増えてきた当時より今の方が増えているので、メディアではなかなかリアルな話を流しにくいのか、我が国を取り巻く環境は非常に厳しいのかと思います。現に私が営業フォローで携わらせていただくのは住宅会社が多いのですが、家を建て始める20代30代の子育て世代がメインだったものの、今は完全に50代、60代の建替え世代の接客をすることがほとんどです。理由は明白。20代30代の所得が増えていないにも関わらず物価や税金が上がっているので、本来お金を使う世代が「身構えて使えない」という状況によって、どんどん悪循環に陥っているのだと思います。経済は心理学。「先行きが不安」となると、当然景気は悪くなります。住宅業界は、着工棟数が地域によっては前年の3割減という状況のエリアもあるのですが、ただこういった話をすると「だからうちは苦しいんだ…」と言い訳に使う会社があるのですが、その際気を付けないといけないことは7割の会社は家が建てられているという現実から目を背けてはいけません。現に弊社クライアント様は絶好調。なぜ絶好調かと言うと「絶好調になるように真剣に必死に頑張っているから」という至極シンプルな話なのです。周りの状況を把握し、対策を練ることは非常に大切ですが、周りの状況に合わせて自分も凹む必要なんて全くないんだぜ?