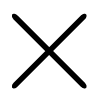BENchmarkブログ
【第1056回】「儲かるからやる」ではなく
長く事業を続けている企業に共通していることは「お金儲け」を一番の目的にしていないということです。逆を言えば「お金」が目的になっている企業や人の活躍できる期間は非常に短いもの。だからこそ弊社も大切にしていることとしては「儲かるからやる」のではなく「人のためになることだからやる」ということを意識しています。何かを購入する際もそう、「これを買って仕事に活かすと儲かりそうだな」という考えではなく「これを購入して活用することによってクライアントがますます楽になりそうだな」や「1社で購入したら高額だから、まずは自分がみんなを代表して購入して必要な人が低予算で活用できるようにしよう」というような考えで取り組む内容や購入するものを決めるようにしています。商売はどこまでいっても「人の役に立つことによって成り立つもの」、それに対して「儲かるかどうか」という考えは自分本位な考え方になってしまうので商売の根本から離れていってしまうので中々長続きしないのかもしれませんね、あなたは今働いている理由としてどこに重きを置いていますか?
【第1055回】大人の嗜み
新成人のみなさま、一日早いですが明日は成人の日ですね。おめでとうございます。21年前成人式に参加した際、久しぶりに会った中学・高校の同級生と再会し、その日に開催された同窓会ではみんなまだお酒にも慣れていないにも関わらず背伸びして自分のキャパもわからず呑んで潰れ、わたしに関しては今思うと急性アルコール中毒だったんじゃないかというくらい悪い呑み方をして3日ほど体調が悪くなって寝込んでおりました。アホだから車で行って、当然呑んだので車で帰れなくなり両親に迎えにきてもらって「ごめんねぇ~」と言った際に二人から「それでいいんやで」「呑んだら乗ったらアカンでちゃんと呼んで偉いよ」と言ってもらったことは両親からしたら当たり前のことを言ってくれただけかもしれませんが、わたしにとっては大袈裟かもしれませんが、「真面目に生きていけば褒めてもらえる」「正直に生きていく方が評価される」と、なぜか腹落ちした瞬間でもありました。幼いときは「ちょっと悪いこと」がカッコいいこと、真面目にコツコツは「ちょっと恥ずかしい」と思いがちですが、大人になったら真面目にコツコツしている人が本当にカッコよく見えて、変に悪ぶっている人を見ると「えぇ~、まだそんな感じ?プププ~!」となっちゃうので面白いものですね、世の「大人」とカテゴリーされているみなさま、わたしも含め「かっこいい大人」になって若人の憧れの存在でいられるよう頑張りましょうね!それが大人の嗜みってやつじゃない?
【第1054回】教育の結果が出るには「時差」が発生する
営業は扱う商品や金額にもよりますが「結果」が出るのはわりかし早いものですが、「教育」に関しては「結果」がでるのにはかなりの「時差」が発生します。早くて5年~10年、もしかしたら「結果」として出てくるのは20年経ってからということもざらではありません。これは教育を「与える側」と「受ける側」のレベルの違いによるものだと思います。例えば親子でも、こどものころは親の一挙手一投足にイライラしたり悲しんだりしていたのが、いざ自分が親になってみると「親の気持ちがわかる」や、仕事においても新入社員のころは上司の言動に不平不満しかなかったものが、自身が部下を持つと「あの上司はめちゃくちゃ良い上司だったんだな」と思ったり、みなさんも心当たりはありませんか?「結果」もどこにゴールを持ってくるかによってその定義は違ってきますが、親や上司のゴールは自身が教育したこどもや部下が「一人で生きていける人材」になることがゴールなのかと思います。そこらへんを理解しておかないと、双方にとって苦しい状況に陥ってしまいます。有難いことに株式会社BENchmarkでは年明け早々「新春研修」として社内研修のご依頼をいただく企業様が複数社いらっしゃいます。今年は嬉しいことに去年研修で講師をさせていただいた企業様から「おかわり」として研修のご依頼をいただいております。「学び」は生きる上でとても大切な機会です。与える側も受け取る側も双方ゴールを明確にし、お互いが「教えて良かった」「教えられて良かった」とお互いが生きているうちに思える人生って素敵じゃない?
【第1053回】事業をする上で一番のリスクは?
事業をしていく上で一番のリスクとはなんでしょう?景気が悪くなること?資金ショートすること?人が辞めること?どれもこれも大変な状況に変わりはないかもしれませんが、一番のリスクは「経営者自身がやる気をなくすこと」です。アントニオ猪木の名言「元気があればなんでもできる」ではないですが「やる気」があれば大抵のことはなんとかなります。「企業30年説」という言葉があります。これは企業が繁栄を謳歌できる期間は平均して30年程度であり、その後は経営環境の変化や事業継承などの壁に直面し多くの企業が衰退・消滅するするという考え方で、1980年代に日経ビジネスが提唱した説です。ただ、現代のビジネス環境ではその期間は更に短くなっているとも言われています。ただ、この「30年」という期間、なんとなく経営者の「やる気」にリンクしている気がします。20代~30代に起業したとしたら30年後は50代後半か60代半ば、おそらく子供も手を離れ場合によっては住宅ローンも支払い切ったか、残債も少なくなりそれまで貯めた蓄えで支払える額にもなり「肩の荷がおりたタイミング」なのでしょう。だからこそ、「もう事業辞めちゃお」となるのでしょうね。一番のリスクは「やる気をなくすこと」。希望と期待、情熱を持ち続け一人で事業を続けていくのは結構しんどいことです。だからこそ、「一緒に走ってくれる存在」がいれば、過酷な旅も「貴重な思い出」になるんじゃない?
【第1052回】仕事はじめ。
2026年1月5日、本日が弊社の仕事はじめになります。改めまして本年も何卒よろしくお願いいたします。みなさん今年の目標は立てましたでしょうか?目標は無理に立てなくても良いし、なんならなくても良いのですが「あった方が願いが叶いやすい」ので弊社顧問先の方には毎年1月は「仕事目標とプライベート目標」を考えることからはじめます。旅行に行くにしても漠然と「今年は旅行行こかなぁ」と思うのと、「いつ、どこに、予算はいくらで、どんなプランで…」と明確に計画を立てた方が叶う確率とスピードは圧倒的に早いのです。ちなみにわたしは2025年に立てた目標は8割ほど達成できました。2026年の目標はどれだけ達成するのか今から楽しみです。とりあえず後厄のお祓いはマッハで行ってきます。あなたは2026年にどんな目標を立てますか?